※本記事にはプロモーションが含まれています。リンクから商品を購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります。
水は“最初に尽きる備え”。
今こそ、家族の命を守る“水の準備”をはじめよう。
この記事では、災害時の水の確保方法や、家庭でできる水の備蓄術をまとめています。
災害時、最も重要なのは「水の確保」です。
電気やガスが止まっても、数日は何とかなることがあります。
しかし、水だけはそうはいきません。人は水がなければ、3日も生きられないのです。
この記事では、防災時に必要な水の確保方法と、備えておきたい「命を守る水グッズ3選」を紹介します。
飲料水・生活用水・浄水――それぞれの用途に合った備えを見直していきましょう。
災害時、なぜ「水の確保」が最優先なのか
災害時には、断水や水道トラブルが最初に起こることが多いです。
飲み水がなくなると、体内の水分バランスが崩れ、脱水症状や体調不良を引き起こします。
さらに、料理・洗顔・トイレなど生活用水も必要です。
「飲める水」と「使う水」、どちらも確保しておくことが、生き延びるための鍵になります。
👉断水時のトイレはどうすれば...こちらの記事で詳しく解説しています。
防災の水、どれくらい必要?
防災の基本として、1人あたり1日3リットル×3日分=9リットルを備蓄するのが目安です。
家族4人なら、最低でも36リットル。
ペットボトル(2L×18本)に換算すると、意外に多い量ですよね。
そのため、「長期保存できる飲料水」や「持ち運びしやすい給水バッグ」、「緊急時の浄水器」を組み合わせて備えるのが現実的です。
防災時に備えておきたい水グッズ3選
① 飲料水の備蓄
災害初期に最も必要なのが、飲料水。
コンビニやスーパーではすぐに売り切れるため、5〜7年保存可能な長期保存水を備えておくのが安心です。
たとえば「あやみず」や「富士ミネラルウォーター」などは、味がまろやかでそのまま飲んでもおいしいのが特徴。
家族人数分を最低3日分、できれば1週間分をストックしておきましょう。安心して飲める水があれば、災害時の食事も安心できます。アルファ米であれば、常温の水でも調理可能。詳しくはこちらで
飲料水の備えが命綱。まずは3日分の長期保存水を確保しましょう。
② 給水・運搬アイテム
避難時や断水後は、水を運ぶ手段が重要です。
ポリタンクはかさばりますが、折りたたみ式の給水バッグなら省スペースで便利。
10〜20Lの容量があるタイプを、1家族につき2つ用意しておくと安心です。
また、バルブ付き・キャスター付きのタイプを選べば、女性や高齢者でも運びやすくなります。
持ち出しにも保管にも便利。折りたためる「給水タンク」で、断水後の命の水を守る。
③ 浄水・濾過グッズ
災害時には「水道水が濁る」「断水後の復旧直後に不純物が混じる」といったケースも多いです。
そんなときに役立つのが携帯浄水器。
「ライフストロー」「ソーヤーミニ」などの携帯タイプなら、川や雨水も飲料水レベルに濾過可能。
また、塩素タブレット(浄水剤)を併用すれば、長期の断水にも対応できます。
川の水も、雨水も“飲める水”に。非常時の命をつなぐ「携帯浄水器」を1本備えておこう。
備蓄水の保管・交換ルール
せっかく備蓄しても、保管環境が悪いと劣化します。
以下の3点を守るのが基本です👇
- 直射日光を避け、冷暗所に保管する
- ペットボトルのキャップを清潔に保つ
- 消費期限が近いものから使い、補充する
「飲む・補充する」を繰り返すローリングストック方式がおすすめです。
まとめ|水の備えは“命の備え”
- 水は防災の最優先項目
- 飲料水・給水バッグ・浄水器の3点セットが鉄板
- 家族の人数に合わせて“使える量”を備える
未来の安心は、今日の準備から。
今こそ、「命の水」を確保しましょう。
💧おすすめの水関連アイテムまとめ
水の備えは、“未来の自分へのエール”。今日のひと準備が、非常時の安心に変わります。


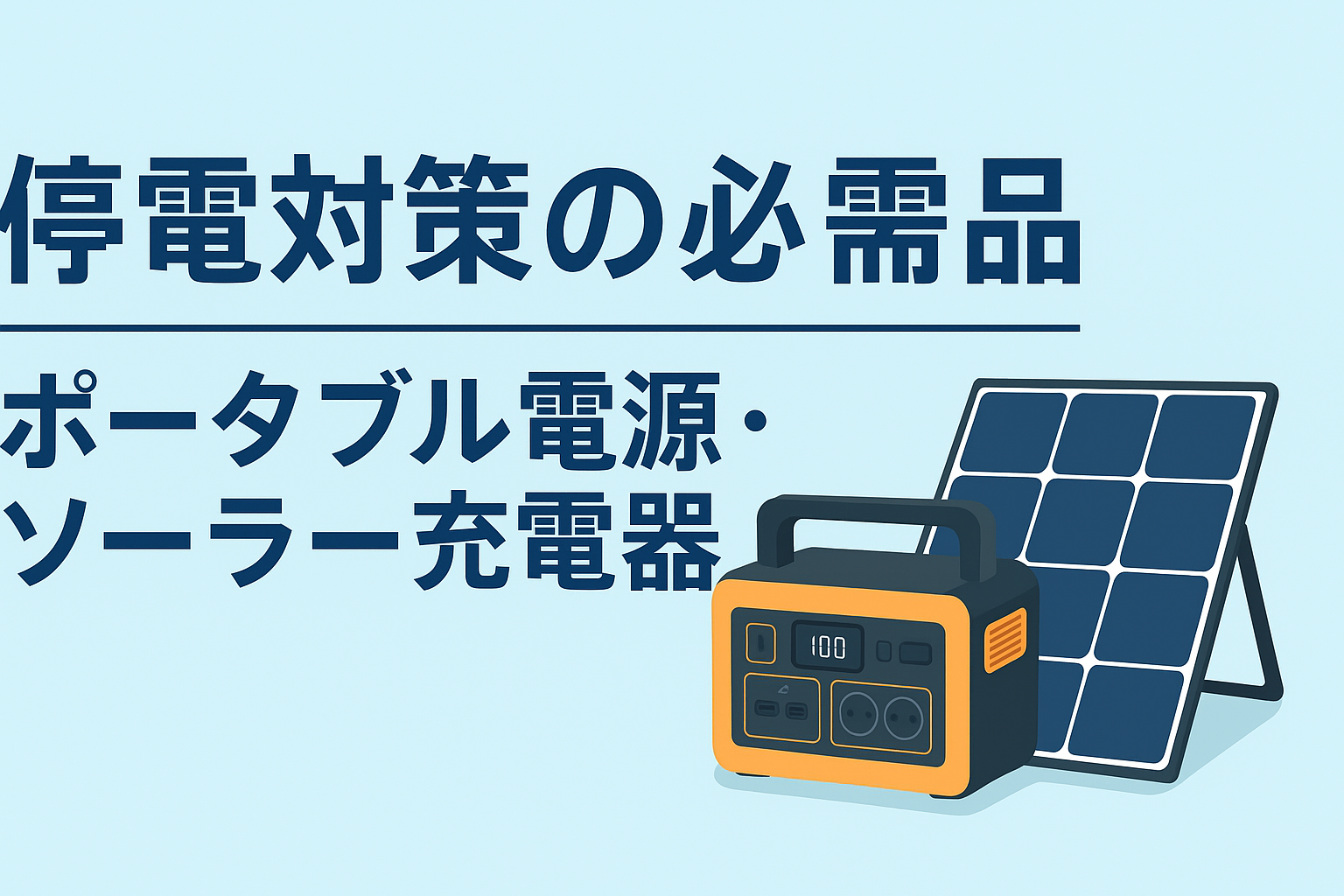
コメント