※本記事にはプロモーションが含まれています。リンクから商品を購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります。
災害はいつ起きるかわかりません。地震・台風・豪雨・土砂災害…いざという時に家族がバラバラになってしまう可能性もあります。そんなときに役立つのが「家族で作る防災マップ」です。
そこで今回は、家族で取り組む防災マップ作りのコツをまとめました。避難所・危険箇所・避難ルートをまとめ、子どもや高齢者、ペット連れでも安心できる工夫を紹介しています。避難所や危険箇所を確認し、実際に歩いて点検。紙とデジタルの両方で備えることで、災害時の安心が増します。自分で活用できるだけではなく、お子様の自由研究や、防災教育にもぜひ。
家族で作る防災マップの基本と効果
防災マップとは、災害時に安全に避難するための場所やルート、危険箇所を一目で把握できる地図です。家族が一緒に取り組むことで、災害時に「誰がどこへ避難するのか」「どの道を通るのか」が明確になり、パニックを防ぐ効果があります。
多くの自治体では「ハザードマップ」が公開されていますが、これは地域全体を対象としたもの。家族で作る防災マップは、自宅や学校、職場といった日常生活の動線に合わせてカスタマイズできるのが大きな違いです。
例えば、家族それぞれにとって重要なのは以下のポイントです。
- 「どこの避難所に行くか」
- 「どの道を通れば安全か」
- 「どこに危険箇所があるか」
これらを視覚化して共有することで、避難行動がスムーズになり、最悪の事態を避けることにつながります。特に小さな子どもや高齢の家族がいる場合、事前に確認しておくだけで命を守る確率が高まります。
また、紙の地図だけでなく、スマートフォンの地図アプリや防災アプリと組み合わせることで、より実用的な防災マップを作ることが可能です。
防災マップの作り方:盛り込むべき情報一覧
家族で作る防災マップは、単なる地図ではなく「命を守るための情報ツール」です。避難所や危険箇所、避難ルートなどをあらかじめ書き込んでおくことで、災害時に慌てず行動できるようになります。特に 「防災マップ 作り方」や「避難所 確認」といった視点を意識すると、実用性がぐんと高まります。
以下の情報を盛り込むのがおすすめです。
- 避難所の位置と連絡先
指定避難所・広域避難所を地図に明記し、住所や電話番号も記載しておくと安心です。子どもや高齢者も迷わず向かえるよう、家族全員で確認しておきましょう。 - 危険箇所のチェック
川沿い、崖、古いブロック塀、倒壊の恐れがある建物など、災害時に危険となる場所をマークします。「危険箇所 チェック」という視点で歩きながら確認するのが効果的です。 - 生活インフラの把握
近くの病院、消防署、交番、給水所の場所を記入。停電や断水が長引いた場合、給水所の位置を知っているだけで行動が変わります。 - 避難ルートを複数確保
自宅から避難所までの安全なルートを1つだけでなく複数用意しましょう。「避難ルート 複数」という考え方が、防災マップの大切なポイントです。 - 連絡手段の確保
公衆電話や災害用Wi-Fiスポットも書き込んでおきましょう。大規模災害時にはスマホが繋がらないケースも多く、緊急連絡の命綱になります。
これらの情報をあらかじめ記入しておけば、災害時に迅速に判断でき、家族の安全を確保できます。。
家庭版・防災マップの作り方:4つの手順
防災マップ作りは、ただ地図に書き込むだけではありません。実際に家族で歩き、危険箇所を確認しながら作ることで、初めて実用的な「家庭版防災マップ」になります。ここでは初心者でも取り組みやすい、4つの手順を紹介します。
手順1:自治体のハザードマップを入手
まずは自治体が提供している 「ハザードマップ」 を確認しましょう。市町村のホームページや役所で配布されています。
- 洪水や土砂災害の危険区域
- 津波の浸水想定範囲
- 指定避難所の位置
といった情報が載っているので、家庭の防災マップのベースに最適です。
前もって危険区域を確認したい方はこちら。
手順2:実際に歩いて危険箇所をチェック
次に、家族で通学路や通勤路を歩きながら、**「危険箇所チェック」**を行いましょう。
例えば、
- 川沿いの道や崖下の道
- 夜間に暗くなる道や細い路地
- 古いブロック塀や倒れそうな建物
などを確認し、地図に書き込んでいきます。実際に歩いて気づく危険は、紙面上だけでは分かりません。
手順3:家族会議でルート・避難場所を決定
危険箇所を洗い出したら、家族会議を開いて避難ルートを決めましょう。
- 「子どもは学校からどの避難所へ向かうか」
- 「高齢者は階段を避けられるルートか」
- 「ペット連れの場合は受け入れ可能な避難所か」
を話し合って決めておくことが大切です。複数ルートを用意しておくことで、通行止めや崩落時にも対応できます。
手順4:紙とデジタル両方で保存
完成したマップは、紙とデジタルの両方で残しておくことをおすすめします。
- 紙:停電や通信障害時でも使える
- デジタル(Googleマップや防災アプリ):共有や更新が簡単
スマホに保存するだけでなく、冷蔵庫や玄関など、家族がすぐに見られる場所に貼っておくと安心です。
家族構成別の工夫:子ども・高齢者・ペット対応
家族で使う防災マ防災マップの作り方は、家族の事情によって変える必要があります。誰が、どこから、どう避難するのかを想定しておくことで、実際の災害時に混乱せず行動できます。
- 子ども
学校から自宅や避難所までの安全な帰宅ルートを明記しましょう。大人が迎えに行けない場合を想定し、子ども自身でもたどれるシンプルな道を選ぶことが大切です。 - 高齢者
足腰が弱い方や体力に不安がある方は、坂道や階段を避けたルートを優先。車椅子や杖を利用しても安全に移動できる道を確認しておきましょう。 - ペット
すべての避難所がペットを受け入れているわけではありません。「ペット同伴可」の避難所をあらかじめ調べ、マップに記載しておきましょう。 - 車椅子利用者
段差や狭い道は避け、バリアフリー対応の施設や避難経路を優先的にチェックしておくと安心です。
このように、家族構成ごとの事情を踏まえてルートを設定しておけば、災害時の避難がスムーズに進み、家族全員の安全を守れる可能性が高まります。
防災マップの活用法と定期的な見直し
日本は世界有数の災害大国であり、地震・台風・大雨・土砂災害など、毎年のように大規模な自然災害が発生しています。だからこそ、防災マップは「作って終わり」ではなく、定期的な見直しと更新が欠かせません。常に最新の状態を保つことで、いざという時に本当に役立つツールになります。
最新情報を家族全員で共有
避難所の位置変更や新しい危険箇所などを反映させ、常に最新状態に保ちましょう。小学生の子どもにも理解できるように色分けしたり、マークを使うとわかりやすくなります。。
年に1回は家族で避難訓練とセットで確認
防災マップを見直す最適なタイミングは、家族での避難訓練と同時に行うこと。避難ルートを実際に歩きながら「この道は安全か」「新しく危険箇所が増えていないか」をチェックしましょう。
災害リスクが高まる前に点検
特に台風シーズン前や大きな地震の後には、必ず点検する習慣をつけるのがおすすめです。インフラ工事や新しい建物の影響で、以前は安全だった道が危険になることもあります。
紙とデジタルの両方を用意
停電や通信障害が発生すると、スマホやPCの地図は使えなくなることがあります。紙の防災マップを作って冷蔵庫や玄関に貼っておけば、非常時でもすぐ確認可能。デジタルは更新や共有が簡単なので、両方を組み合わせるのが最強です。
まとめ|今日から家族で防災マップを作ってみよう
防災マップは、家族の命を守るための大切なツールです。
- 避難所や危険箇所を確認し、
- 家族構成に合わせたルートを決め、
- 定期的に見直すことで、
いざという時に慌てずに行動できるようになります。
「自分の地域は大丈夫」と思っていても、災害は突然やってきます。紙とデジタルの両方で防災マップを用意し、家族全員で共有しておくことが、最もシンプルで確実な防災対策です。
👉 まだ作っていない方は、今日からでも始めてみましょう。まずはハザードマップを入手し、家族で一緒に歩きながら危険箇所をチェックすることが第一歩です。小さな行動が、大切な家族の命を守る大きな備えにつながります。
防災マップと一緒に用意したい、防災対策グッズの記事もあわせてお読みください
- 初めての防災準備|最低限そろえるべき12アイテム
- 非常用持ち出し袋チェックリスト(家族構成別)
- 備蓄食料の選び方|保存期間・栄養・調理のしやすさ比較
- 災害時の水確保マニュアル|保存水・浄水器・雨水利用
- 停電対策の必需品|ポータブル電源・ソーラー充電器
- 防災ラジオの選び方|手回し・ソーラー・電池式の違い
- 災害時のトイレ問題解決|携帯トイレ・簡易トイレ徹底比較
よくある質問(FAQ)
防災マップはどのくらいの頻度で更新すべきですか?
少なくとも年に1回は更新しましょう。特に台風シーズン前や地震後には、避難所や危険箇所の状況が変わる可能性があるため、最新情報を反映させることが大切です。
防災マップは紙とデジタルのどちらが良いですか?
両方を用意するのがおすすめです。紙は停電や通信障害時にも使え、デジタルは更新や共有が簡単です。併用することで災害時にも安心です。
子ども向けの防災マップの工夫はありますか?
子どもでもわかるように、色分けやイラスト、シンプルなルートを使うと安心です。避難訓練と合わせて活用すると、実際の行動に結びつきやすくなります。
ペットを飼っている場合、防災マップに何を追加すべきですか?
ペット同伴可能な避難所の位置や連絡先を必ず記入してください。また、避難経路の途中でペットの安全を確保できる場所も確認しておくと安心です。
防災マップはどこから始めれば良いですか?
まずは自治体が提供している「ハザードマップ」を入手し、それをベースに自宅周辺を歩きながら危険箇所や避難所を記入していきましょう。家族で一緒に作ることが大切です。

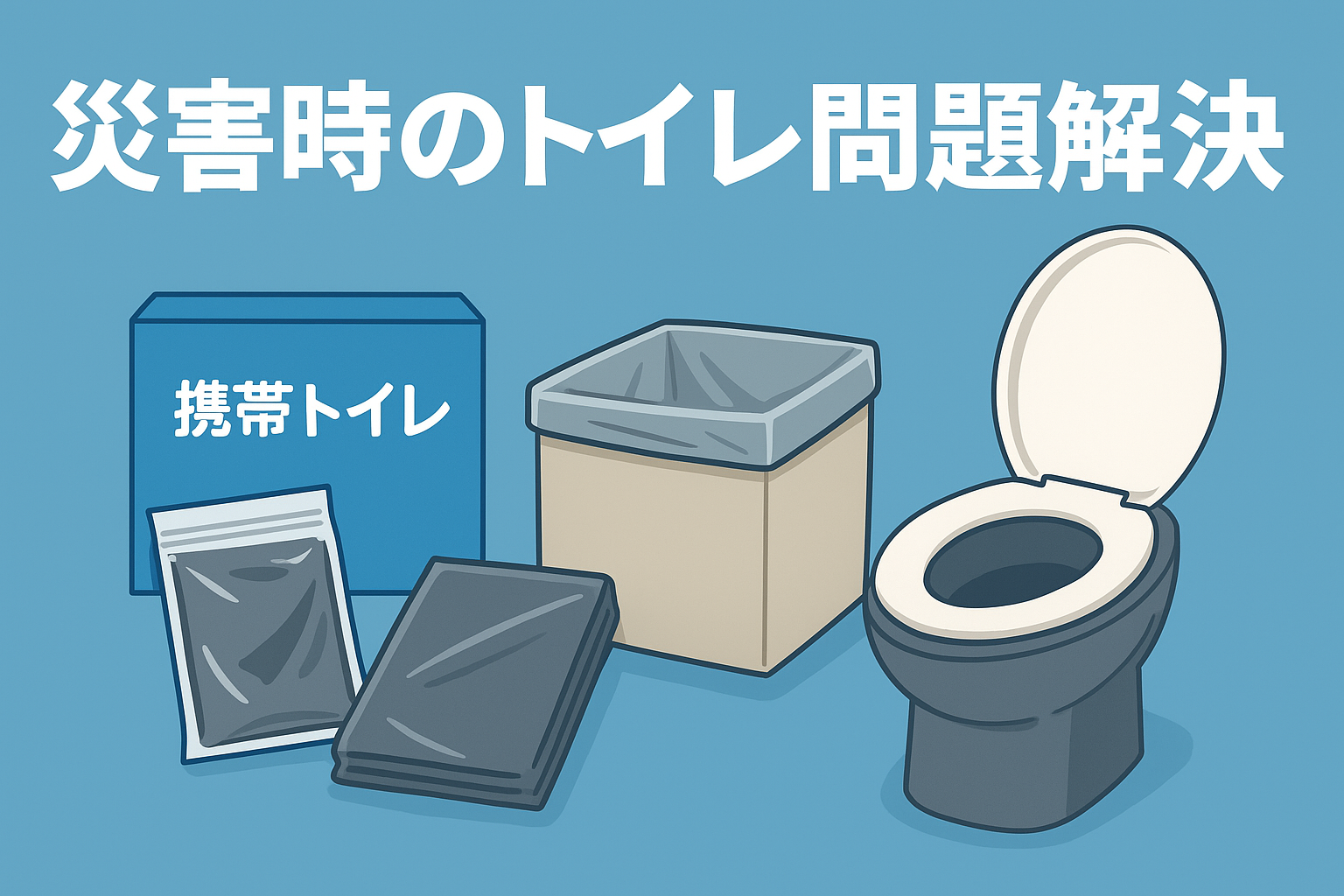

コメント